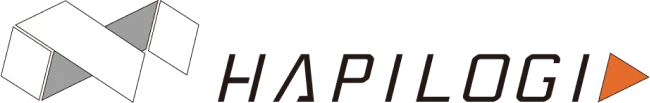2025.04.21
物流業界で注目を集める3PLとは|メリット・デメリット

複数ショップに出店したり、複数の倉庫と提携したりと事業を拡大しているEC事業者にとって、物流業務は大きな課題となっています。業務負担の軽減やコスト削減のため、アウトソーシングの需要が高まり、物流サービスを提供する業者も数多く存在しています。「3PL」もそのひとつです。同じく物流業務をアウトソーシングする「フルフィルメント」との違いや、メリットとデメリット、導入時の注意点について紹介します。
目次
物流を最適化する「3PL」とは

まずは3PLについて知っておきましょう。
3PLの概要
3PLとは「3rd party logistics」の略であり、直訳すると「第三者の物流」で、物流に関する業務を包括的に請け負うサービスを意味します。業者にもよりますが、商品の受発注や在庫管理、ピッキング、検品、梱包を経て、配送まで行うのが基本です。
アセット型とノンアセット型があり、前者は自社でトラックや倉庫、人員を保有してサービスを提供します。後者は自社が窓口となり、クライアントの要望に応じて、提携しているほかの業者に外注する形式です。
フルフィルメントとの違い
3PLと同じく、物流業務を包括的に請け負うサービスに「フルフィルメント」があります。両者の違いは、請け負う業務の範囲です。
先述のとおり、3PLは物流に関する業務だけを請け負うのが基本ですが、フルフィルメントでは物流に付随する業務まで請け負います。例えば、決済代行や入金・返金の管理、顧客対応などです。
3PLを導入するメリット・デメリット

続いて、3PLを導入するメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット
3PLを導入するメリットは、大きく分けて3つあります。ひとつひとつ説明していきましょう。
1.経費の削減と適正化につながる
自社で物流業務を行うと、倉庫や車両の維持費、運送にかかる費用、従業員の人件費などが発生します。これらは発送の多い少ないにかかわらず、金額が決まっている固定費です。3PLは、発送の量に応じて料金が変動する従量制なので、発送が少ない月は費用を節約できます。
2.生産性と顧客満足度の向上につながる
3PLを提供するのは物流の専門家ですから、業務を効率化するのは得意です。その結果、迅速で間違いが少なく、大量の発送も可能になり、コストを削減しつつ、売上を増やして顧客満足度も高めることができます。
3.コア業務に専念できる
物流業務を自社だけで行うのは、費用面の負担が大きいだけでなく、限られた人員も割り当てなければいけません。繁忙期には、ほかの部門の社員も応援に入らなければならず、本業が機能しない場合もあるでしょう。
3PLに物流業務をアウトソーシングすれば、マーケティングや集客、販売など、本来力を入れるべきコア業務に専念できます。
デメリット
3PLに物流業務をアウトソーシングするデメリットは、大きく分けて2つです。
1.自社内にノウハウが蓄積されない
自社内で物流を担える人材を育成できず、いつまでも3PLに頼らざるを得なくなる可能性があります。特に、自社で物流を内製化できるほどの規模を持つ、大企業やメーカーでは大きなデメリットになりやすいでしょう。
3PLの導入で、こうしたデメリットを上回るリスクを回避できたり、生産性の向上が見込めたりするのか、事前に検討したいところです。
2.問題への対処が遅れるおそれがある
どのように物流業務が運用されているのか自社で把握しづらく、経営上の問題が発生しても、原因を特定するまで時間がかかるというデメリットもあります。利用にあたっては、自社内で物流に精通した担当者を設け、3PL業者との窓口になってもらうと良いでしょう。
3PLを導入する際の注意点

3PLにメリットがあっても、業者側で適切に運用されていなければ意味がありません。導入にあたっては、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
コミュニケーション体制が重要
単に物流業務を丸投げしても、3PLだけで満足できるサービスを提供するのは限界があります。自社に合った物流管理ができなければ、発送の遅延などのトラブルにつながってしまうでしょう。運用方針や物流管理について、自社と3PL業者の双方で情報を共有できる体制を作るのが大切です。
窓口となる担当者を介してコミュニケーションを取るのはもちろん、社内の誰が見ても分かる物流業務のマニュアルを作っておくのも良いでしょう。
大幅なコスト削減につながらないことも
物流業務のアウトソーシングにかかるコストは、3PL業者によってまちまちです。見積もりを取っても、期待したほど安くならない場合もあります。だからといって、価格を優先して3PL業者を選ぶと、物流の品質が低下して客離れを引き起こす原因になってしまいます。
3PL業者を選ぶときは、目先のコストだけにとらわれず、中長期的な視点で判断するようにしましょう。
自社に合った業者を選ぶ
3PL業者は、それぞれ規模や委託できる業務内容、料金設定が異なります。自社の目的に合ったサービスを選ばなければ、期待したほどの成果が得られないこともあるため注意が必要です。
自社に合ったサービスを選ぶには、以下のポイントを見てみましょう。
1.必要坪数
2.出荷件数
3.導入の目的
まずは「必要坪数」です。3PLのシステム利用や業務管理、倉庫の保管にかかわる費用は、利用する坪数によって決まります。これらは出荷の量にかかわらず固定です。安価なシステムを利用したり、土地代の安い地方に倉庫があったりするなどして、同じ坪数でも手頃な価格を提供している3PLもあります。
もちろん、必要な坪数を提供できる業者でなければいけません。今後、事業が拡大する見込みがあるなら、柔軟に拡張できるところを選ぶと良いでしょう。
次に「出荷件数」です。出荷にかかる費用は個数ごとに定められており、商品の大きさや種類によっても異なります。自社で最も扱う量が多い商品の大きさや種類を確認し、これらの価格設定が安い業者を選ぶと、コストを抑えられるでしょう。
なお、業者によっては、繁忙期になると追加料金を請求するところもあります、最も出荷量が多いときに、どれくらいの費用が上乗せされるのか必ず確認しましょう。
そして、3PLを導入する目的によっても、選ぶべき業者は変わります。単に代行してほしいのか、コストを抑えたいのか、物流サービスを充実させたいのか、などです。
目的によって業者に求める条件も違ってくるでしょう。例えば、物流サービスを充実させたいのであれば、業者との連携を重視したいところです。目的や条件が複数ある場合は、優先順位をつけて上位を満たせるところを選びましょう。
自社に合った物流アウトソーシングなら

倉庫選びで迷ったときは、“仕組み”で解決するという選択も
EC物流倉庫を選ぶうえで、「立地」「温度帯」「作業対応範囲」「コスト」などの条件をすべて満たす理想的な倉庫を見つけるのは簡単ではありません。
仮に理想に近い倉庫が見つかったとしても、
「システム連携が不十分で、結局EC事業者側が手作業を担う必要がある」というケースは少なくありません。
-
倉庫側で使われているWMSと自社システムが合わない
-
注文データや出荷データの形式が異なり、手動で変換が必要
-
作業指示書の出力や入荷データの整備が毎回手間…
特に、物流やシステム連携に不慣れな企業にとっては、「どこから手をつければいいのか分からない」という理由で、導入を見送ってしまうケースもあります。
logiecなら、ECと倉庫の“つなぎ目”を自動化できます
はぴロジの自社開発システム「logiec(ロジーク)」は、こうしたEC物流の“つなぎ目の課題”を根本から解決する仕組みです。
-
あらゆるECモール・カート・受注管理システムと連携可能
-
注文データや出荷実績の自動変換・自動取り込みを実現
-
WMS(倉庫管理システム)との接続により、出荷指示も自動化
つまり、ECと倉庫、両方に詳しくなくても、logiecが間に入ることで物流のDXが実現します。
「倉庫探しから運用まで」まるごと任せたい方には、物流アウトソーシングサービスも
「そもそも自分たちで倉庫を探したり、比較検討するのが難しい…」という場合には、
はぴロジの物流アウトソーシングサービスをご活用ください。
-
EC業態や取扱商品に最適な倉庫を提案
-
保管・出荷・加工業務までトータルでサポート
-
logiecとの連携で注文から出荷までを自動化
ヒト・モノ・システムが揃った最適な物流体制を、ワンストップで実現することが可能です。
まとめ
3PLでは、物流業務に特化したアウトソーシングを行っています。業務委託により、担当者の負担を軽減できるほか、コスト削減にもつながります。
導入にあたっては、目的を実現できるサービスを選び、自社と業者の双方で情報共有ができる体制を作ることが重要です。
閲覧ランキング
おすすめ記事
記事検索