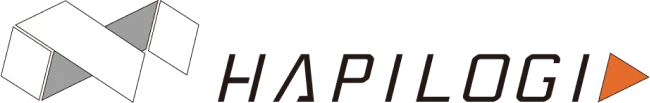2025.04.21
WMSとは?主な機能やデメリットを解決できるシステムを紹介

倉庫の運営・管理の課題は、「WMS(倉庫管理システム)」の導入で解決できる可能性があります。導入にあたっては、WMSについて理解しておきたいところです。WMSの定義や必要性、メリット、デメリットについて紹介します。
目次
WMS(倉庫管理システム)とは?

WMSは、倉庫内全般の運営・管理をサポートするシステムです。入荷時にバーコードを発行して、ハンディスキャナで読み取り、在庫状況をリアルタイムで把握できるようにするのが一般的な仕組みです。
主な機能は以下です。
| 入荷管理 | 商品の個数や要件が合っているかを確認できる。 |
|---|---|
| 在庫管理 | 庫内にある商品の在庫状況を管理できる。 |
| 出荷管理 | 出荷指示書の作成や、納品物の情報確認ができる。 |
| 棚卸し管理 | 商品の数量がデータと一致しているかを確認できる。 |
| 返品処理 | トラブルがあった商品を受け取ったり、返金したりできる。 |
| 帳票・ラベル発行 | 納品書や発注書などの帳票類や、ラベルの発行ができる。 |
これらの機能によって、倉庫内の実在庫はもちろん、商品がどこに何個、どのような状態で保管されているか、把握することができます。
WMSの中には、独自の機能を設けて、利便性を高めているものがあります。
例えば、マテハン(マテリアルハンドリング機器)や物流ロボットと連携できる機能が備わっているタイプです。また、定期通販向けの便利な機能が備わっているなど、特定の物流方法に対応できるWMSもあります。
基幹システムや在庫管理システムとの違い

WMSと同様に、基幹システムや在庫管理システムでも在庫状況を把握することができます。それぞれ、どのような違いがあるのか見てみましょう。
基幹システムとの違い
基幹システム(ERP)は、企業のあらゆる業務における情報を一元管理するものです。社内で同じ情報を共有できるので、業務を効率化できたり、経営判断に役立てたりすることができます。
ただし、基幹システムの物流部門は在庫状況を把握できるだけで、倉庫の運営・管理まではできません。検品や仕訳、帳票類の発行、ピッキング、保管場所の決定などは、WMSのほうが得意といえます。
在庫管理システムとの違い
在庫管理システムは、商品の在庫管理に特化しています。仕入れ先や出荷先の情報を把握した上で、商品の過不足が生じないように在庫を管理します。WMSでも在庫管理はできますが、対象範囲は倉庫に入荷してから出荷するまでに限られます。
ただし、在庫管理システムにはWMSのような倉庫業務の運営・管理で必要となる機能は搭載されていないケースがほとんどです。
WMS(倉庫管理システム)を導入するメリット
では、WMSを導入すると、どのようなメリットを得られるか見てみましょう。
作業の効率化と標準化ができる
従来の人力に頼る方法では、商品の数え間違い、入力間違いで在庫の数が合わなかったり、発送ミスが起こったりする場合がありました。
WMSを活用すれば、多くの作業をデジタルに頼ることができます。間違いがあればアラートで指摘されるため、こうしたトラブルを防げます。
これまで目視で行っていた作業が、バーコードを読み取る作業で済むので、工数削減にもつながるでしょう。倉庫の運営・管理を効率化できるだけでなく、特定のベテランに依存するという属人化を解消し、誰でも同じ作業ができるようにもなります。
正確な在庫がリアルタイムに把握できる
バーコードで読み取った情報はリアルタイムでWMSに反映されるため、在庫情報はいつでも最新の状態に保つことができます。外部システムと連携すれば、別の倉庫の状況も一括で確認できるほか、取引先と情報を共有することも可能です。
さらに、数量だけでなく、「仮置き中」や「保留品」などのステータスも把握できます。返品があった際も、プロセスごとにステータスを変更することでスムーズに管理できます。
これらの機能によって、仕入れや出荷指示などを迅速かつ適切に行えるようになるでしょう。
コストを削減できる
作業の効率化ができれば、人員や残業時間を減らすことができ、人件費の削減につながります。
また、適切な在庫管理によって余剰やロスによる無駄を防げます。販売機会を失わず、収益の最大化が期待できます。
WMS(倉庫管理システム)を導入する際の注意点

WMSには多くのメリットがある反面、漠然と導入しても効果を得られないことがあります。どのような点に注意して導入すれば良いのでしょうか。
導入目的が曖昧だと効果が得られないことがある
WMSは数多くのメーカーから販売されており、それぞれ搭載されている機能が異なります。必要な機能が搭載されてない上に、使い勝手が悪いと、かえって現場を混乱させる原因になります。うまく運用されなければ、導入にかけた費用も無駄になってしまうでしょう。
倉庫の運営・管理におけるどのような課題を解決すべきかを明確にした上で、WMSを選ぶのが理想です。例えば、人件費を削除したいのか、在庫のロスを防ぎたいのか、発送のミスを防ぎたいのかなど、現場の声を聞いて本当に欲しい機能をピックアップしておきましょう。
また、機能で比較するのはもちろん、類似する業態や規模の企業における導入事例も参考になります。
導入から稼働までにコストがかかる
WMSには以下の3種類があり、コストや導入期間は以下の通りです。
| オンプレミス型 | パッケージ型 | クラウド型 | |
| コスト | 高 | 中 | 低 |
| 導入期間 | 長 | 短 | 短 |
オンプレミス型は自社に合った機能を搭載できる反面、開発に莫大な初期費用がかかります。サーバーの用意が必要なほか、導入期間も長いのが難点です。
パッケージ型は初期費用を抑えられ、導入期間も比較的短いです。ただし、自社向けの機能を搭載するにはオプションの追加が必要となるケースがほとんどで、その場合は費用がかかります。
クラウド型は、初期費用を抑えながら導入できます。簡単な設定だけ済ませればすぐに導入が可能で、バージョンの更新も自動で行われます。ただし、毎月の利用料が発生するため、長期で利用するほど割高になるかもしれません。自社向けの機能を追加するのも難しいです。
WMSの導入にあたっては、コストに見合った効果を得られるか検証しましょう。
現場のニーズとマッチしているか
システムを実際に運用するのは現場の担当者です。必ず現場にヒアリングを行い、候補となるWMSが、業務フローやスキルにマッチしているか確認しましょう。
例えば、WMSの「ロケーション管理」は、倉庫の空きスペースを有効活用できる便利な機能です。しかし、保管場所の変更によって、従業員が混乱するなど、作業効率が低下するおそれがあります。
また、仕入れ先や運送会社、ECサイトなど関係機関のシステムと連携できなければ、データの共有ができません。
このように、現場に即したシステムでなければ、大きく管理方法が変わったり、運用されなくなったりします。
現場の教育が必要となる
WMSを導入する際は、実際に操作する従業員への教育やマニュアルの作成が必要です。機械に疎くても直感的に操作できるようなWMSが望ましいでしょう。
また、サポートが充実しているベンダー、もしくはシステム会社であれば、トラブルが発生した際も、すぐ対応してもらえます。サポート体制が整っているところであれば、安心です。
WMSだけではカバーしきれない。物流全体の最適化には“つなぐ仕組み”が必要
倉庫管理システム(WMS)を導入することで、倉庫内の在庫管理や作業効率の改善は実現できます。
しかし一方で、物流全体を最適化するにはWMSだけでは不十分という課題も見えてきます。
たとえば…
-
ECモールやカートごとに異なる出荷データのフォーマット
-
モール側の仕様変更に伴うシステム更新作業
-
倉庫外(仕入れや販売チャネル)とのデータ不整合による誤出荷リスク
こうした課題を根本から解決するには、「倉庫」と「販売チャネル」間を柔軟につなぐ仕組みが必要です。
logiecなら、ECの“物流のつなぎ目”を自動化できます
はぴロジが提供する自動出荷管理システム「logiec」は、
あらゆるECモール・カート・受注管理システムと連携し、フォーマット変換やデータ連携を自動化します。
-
複数モールからの注文データをlogiecが自動で取得
-
倉庫管理システム(WMS)と連携して出荷指示を自動送信
-
出荷実績や在庫情報もAPIまたはCSVで自動反映
これにより、システム間のデータ差異によるミスや、属人的な手作業をなくすことが可能になります。
物流そのものを任せたい方には「物流アウトソーシング」もおすすめ
「そもそも物流全体を外部に任せたい」という方には、はぴロジの物流アウトソーシングサービスもおすすめです。
-
EC業態に適した倉庫・立地のご提案
-
出荷・保管・流通加工までワンストップ対応
-
logiecとの併用で“受注から出荷まで自動化された倉庫運用”が実現
自社でWMSを導入するのが難しい場合も、アウトソーシングという選択肢で確実かつ柔軟な物流体制を整えることができます。
閲覧ランキング
おすすめ記事
記事検索