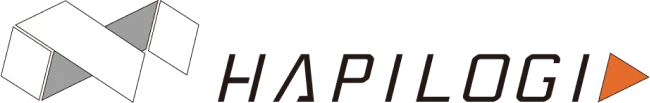2025.04.21
【EC物流の基本】3温度帯とは?常温・冷蔵・冷凍の違いと倉庫選びのポイント
EC物流を検討する際、「3温度帯」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
物流倉庫は、ただモノを保管するだけでなく、温度管理や作業環境の違いによって大きく3つの温度帯に分かれています。
この温度帯の違いは、保管できる商材や物流コスト、倉庫の選定難易度にも大きく影響します。
本記事では、3温度帯の基礎知識から、それぞれの特徴・費用感・倉庫選びのポイントまでわかりやすく解説します。
目次
3温度帯とは?

物流倉庫における「3温度帯」とは、以下の3つの温度環境を指します。
| 温度帯 | 呼称 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 常温(ドライ) | 約10~20℃ | 一般的な日用品・雑貨・アパレルなど |
| 冷蔵(チルド) | 約5℃〜−5℃ | 生鮮食品、スイーツ、飲料など |
| 冷凍(フローズン) | −15℃以下 | 冷凍食品、アイスクリームなど |
各温度帯の特徴と注意点

常温(ドライ)
最も一般的な温度帯で、常温保管が可能な商材の取り扱いが中心です。
倉庫数も多く、比較的探しやすいため、EC物流のスタート地点に適しています。
✔ 倉庫によっては庫内の気温が季節で変動する場合もあるため、事前確認が重要です。
冷蔵(チルド)
温度変化に弱い食品や飲料の保管に用いられます。
庫内は低温維持されており、品質保持のために24時間温度管理がされています。
冷凍(フローズン)
−15℃以下の環境で保管する冷凍食品向けの温度帯です。
冷凍倉庫は数が少なく、空きが出にくい傾向があるため、早めの倉庫確保が重要になります。
冷蔵・冷凍倉庫はコストにも注意
冷蔵・冷凍倉庫は、温度維持のための電力・設備・人件費が高く、
常温倉庫に比べて保管費用や作業コストが割高になる傾向があります。
-
冷蔵:温度管理設備が常時稼働、人件費も高め
-
冷凍:作業環境が厳しく、特にコストがかかりやすい
そのため、商材の特性と物流コストのバランスを見ながら倉庫を選ぶことが大切です。
倉庫探しは、温度帯以外の“目に見えない要素”も重要
温度帯の選定は倉庫探しの第一歩ですが、以下のような点も成功のカギになります。
-
商材への対応実績(ラッピング・流通加工の可否など)
-
エリア・拠点数(分散出荷・リードタイムの短縮)
-
WMSやOMSとのシステム連携可否(API対応など)
こうしたポイントを見落としてしまうと、物流コストがかさんだり、運用に支障が出たりするリスクもあります。
最適な温度帯倉庫のご提案もお任せください
はぴロジでは、EC物流に強い全国200以上の提携倉庫の中から、
商材や温度帯、エリア、出荷量などに合わせて最適な倉庫をご提案しています。
さらに、自動出荷が可能な流通統合システム「logiec」を活用すれば…
-
モールやカートからの受注を自動で取り込み
-
倉庫へ出荷指示をAPI/CSVで自動送信
-
冷凍・冷蔵・常温の3温度帯の分散出荷にも対応
物流業務の効率化とコスト最適化の両立が実現できます。
まとめ
「3温度帯」は、商材の特性や品質保持に直結する重要な物流条件です。
温度帯の違いやコスト構造を正しく理解したうえで、自社に最適な倉庫を選ぶことが成功のカギになります。
物流まわりでお困りの際は、ぜひはぴロジにご相談ください。
倉庫選定から運用構築、出荷システムの導入支援まで、ワンストップでご支援いたします!
閲覧ランキング
おすすめ記事
記事検索